『これが人間かーアウシュヴィッツは終わらない』 プリーモ・レーヴィ著
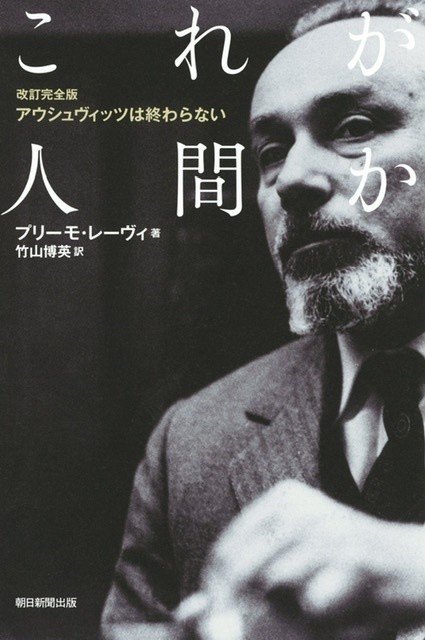
24歳の時、スイス国境近くのイタリアで捕まり、今はなきアウシュヴィッツの労働収容所にあたる巨大な化学工場を有した第三収容所モノヴィッツ(Monowitz)に送られたユダヤ系イタリア人のプリーモ・レーヴィの体験記。
淡々と書かれた醜さ悲惨さでうめつくされた地獄は、『神曲』や詩の引用により押し込められた感情を代弁しているようだった。また、章ごとの断片的な時系列や書き方も混乱と切迫感が伝わってくる。
“持つものには与え、持たないものからは奪え”(本文より)
おごった考え方だと承知で言うが、人が人足らしめるものの一つが良心と名付けている社会秩序に植えつけられた感情なんだと思う。人も獣も植物もひとまとめにするならば、上記の言葉は自然界の掟そのものである。原始的な生存競争の法則に支配されている収容所では、まさに。
性が剥き出しの中での、レーヴィの人間への観察眼は、非常に興味深い。
性が剥き出しの中での、レーヴィの人間への観察眼は、非常に興味深い。
最終章の「十日間の物語」は、狂気の秩序がなくなり、空白による混沌の中での話で、とても知りたかった部分だった。
彼らの状況を表現するには筆舌に尽くし難く、いかなる陰惨な形容詞を使ったとしても、言葉足らずになるのだろうと思う。仏新聞社ル・モンドの『20世紀の100冊』(1999)などにも選ばれている。
彼らの状況を表現するには筆舌に尽くし難く、いかなる陰惨な形容詞を使ったとしても、言葉足らずになるのだろうと思う。仏新聞社ル・モンドの『20世紀の100冊』(1999)などにも選ばれている。
『休戦』 プリーモ・レーヴィ著
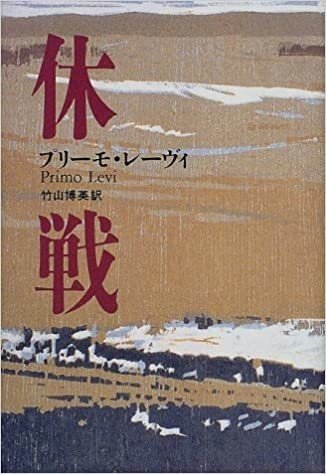
“その時が来たのだと分かったのだった。私たちは森で火をたいた。誰も眠らなかった。その夜は歌い踊って過ごした。そしてお互いに過去の冒険を語り、失った仲間を思い出した。なぜなら人間には、かげりのない喜びを享受することなど許されていないからだ。”(本文より。転々と一時収容所へ移動していき、ベラルーシ(当時のソ連)の収容所から、最終的にイタリアへの帰還が決まった時。)
開放から帰郷へ(1945年1月27日-10月19日)。アウシュヴィッツの解放者がソ連軍だったこともあり、イタリアとは逆方向のソ連領へと一時的に移動することになり、そこからイタリアのトリーノへの帰還を果たす。その道のりはとても長く、また人間性や心などを取り戻すための行程でもあり、これほどまでに帰郷の意味が重いことがあるのだろうかと思った。
全体の分量から考えても、最後の数章でサラッと書かれているが内側へと重く深くなる最後の列車でのベラルーシからトリーノへの長い行程の中、唯一ドイツを通過することになったミュンヘン(オーストリアからミュンヘン経由でイタリアへ入る)での記述を長めの引用。
“私たち汽車は駅に座礁したように止まっていたが、そのまわりはがれきだらけだった。そうしたがれきだらけのミュンヘンをうろつき回ると、支払い不能の債務者の群れの中を歩いているような気分になった。おのおのが私たちに何かを追っていたが、それを払うのを拒否しているのだ。私は今彼らの中にいた、「支配者の民族」の中に、アグラマンテの野営地の中に。だが男たちは少なく、多くは不具で、私たちと同じようにぼろをまとっていた。彼らの一人一人が私たちに問いかけ、何ものか顔で読み取り、謙虚に私たちの話に耳を傾けるべきだ、と私には思えた。だが誰も私たちの目を見ようとしなかった。誰も対決しようとしなかった。彼らは目を閉じ、耳をふさぎ、口をつぐんでいた。彼らは廃墟の中にこもっていたが、それはあたかも責任回避の要塞に意図的に閉じこもっているかのようだった。彼らはまだ強く、憎悪や侮蔑をまた表に出すことができ、高慢と過ちの古い結び目にいまだにとらわれていた。
私は彼らの中に、その封印された顔を持つ無名の群集の中に、別の顔を、よく覚えていて、多くが特定の名を持っている顔を探しているのに気づいて、我ながら驚いた。それは知らないことはあり得ず、忘却は許されず、答えないことはできないものたちだった。命令し、従ったものたち、辱め、堕落させ、殺したものたちだった。それはむなしく愚かな企てだった。なぜなら彼らではなく、別のものたちが、少数の正義にかなったものたちが、その代わりに答えるはずだったからだ。”(本文より)
『これが人間か』でも感じたが、人間観察の巧みさは素晴らしい。大収容所で生と死の境にいた人たち、傷を抱えた人たち、介抱する者たち、解放者でもあるソ連軍人、同胞イタリア人、ギリシア人、フランス人、ポーランド人、アメリカ軍人、そしてドイツ人など…お国柄のような性質として捉えた描写もあるが、深く関わっていき個人の性質として書いている部分もある。
最初の行程を共にしたギリシア人のモルド・ナフムについての章での彼の人生観や労働に対する考え方に唸り、収容所での顔見知りで途中で再会し最後の方まで一緒だった同郷イタリア人のチェーザレの生き方に感心する。
その中で、1人だけ、ここで詳しく引用しておく。
本書序盤、アウシュヴィッツが解放され、収容所はそのまま収容者の一時的な療養施設と変わった。
レーヴィの療養部屋中で一番小さく、無力で、最も無垢な存在だが、注意を逸らすことができぬほどに自らの存在を主張し続けた魂の塊・フルビネクについて、
外見は3歳くらい、下半身麻痺で足が萎縮し、小枝のように細い体、口は聞けず、名もなかったアウシュヴィッツの子供、フルビネク(レーヴィたちが付けた通称)。痩せて尖った顎の顔の中で物言えぬ口を代弁するように圧倒的な力をたたえた瞳は欲求と力と苦痛に満ちていたという。
レーヴィの療養部屋中で一番小さく、無力で、最も無垢な存在だが、注意を逸らすことができぬほどに自らの存在を主張し続けた魂の塊・フルビネクについて、
外見は3歳くらい、下半身麻痺で足が萎縮し、小枝のように細い体、口は聞けず、名もなかったアウシュヴィッツの子供、フルビネク(レーヴィたちが付けた通称)。痩せて尖った顎の顔の中で物言えぬ口を代弁するように圧倒的な力をたたえた瞳は欲求と力と苦痛に満ちていたという。
“フルビネクは3歳で、おそらくアウシュヴィッツで生まれ、木を見たことがなかった。彼は息を引き取るまで、人間の世界への入場を果たそうと、大人のように戦った。彼は野蛮な力によってそこから放逐されていたのだ。フルビネクには名前がなかったが、その細い腕にはやはりアウシュヴィッツの刺青が刻印されていた。フルビネクは1945年3月下旬に死んだ。彼は解放されたが、救済はされなかった。彼に関しては何も残っていない。彼の存在を証明するのは私のこの文章だけである。”(本文より)
『朗読者』 ベルンハルト・シュリンク著
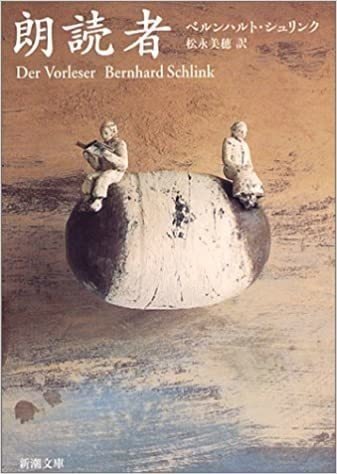
映画化されたが、読後に観た。この順番でとても良かった。(『愛を読むひと』の感想は、映画編に書きます。)
主人公の心の機微の表現がとても丁寧で、共感性も高く溶け込んでくる。
愛するとは、罪とは、真実とは、許すとは…
主人公の心の機微の表現がとても丁寧で、共感性も高く溶け込んでくる。
愛するとは、罪とは、真実とは、許すとは…
“「…あなただったら何をしましたか?」”(本文より)
考えれば考えるほどわからなかった
私ならどうしたか
それを考え続けたとして、愚かで弱く小さな私は、答えを出せず動けないだろうと思う。そんな人間が、他人を糾弾し罰することなどできるはずもない、いや、そもそもしてはならない。
私ならどうしたか
それを考え続けたとして、愚かで弱く小さな私は、答えを出せず動けないだろうと思う。そんな人間が、他人を糾弾し罰することなどできるはずもない、いや、そもそもしてはならない。
彼女の頑なさや言動の理不尽さの理由を知った時に、なんとも言えない気持ちになる。
『アンネの日記(完全版)』 アンネ・フランク著
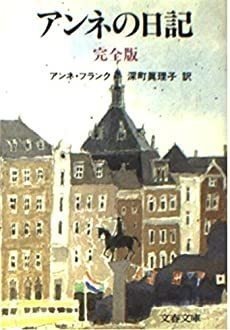
読む前までは、戦時中の隠れ家でのユダヤ人少女の暗く悲しい日記という勝手な思い込みがあった。
だが、(不自由な生活を送ってはいるけれど)普通の思春期の女の子の日記だった。
プライベートな日記を盗み読む背徳感すらある。むしろ男性は読みにくいのではないか…これは同世代の少女たちが読むべきだと思う。
私は彼女の晩年を知り、そして、その生きていた場所を実際に見てきた。
アンネの日記を読みながら、頭の中で何度も再生される収容所での様子が頭をチラついてしまう。12〜14歳の彼女が喧嘩し、怯え、恋し、ユーモアを交えて笑い、夢を語り、クルクル動く感情のその全ての文章の隙間に、対極にある収容所での姿が常に重なり、本の中の彼女が生気に満ちていればいるほど、その落差に胸が苦しくなった。原文ではないから、果たしてどれほど翻訳の妙が冴え渡っているかわからないけれど、10代の感性が飛び跳ねていた。
アンネフランクをよく早熟な少女と表現することがある、例えば、異性や性に対してもあけすけなく興味を持っていたし、人間観察も自己分析もよくしていた。
近年、アンネの日記の、いわゆる”袋とじ”部分の解析ができて、性的なジョークが書かれていたと発表された。でも、そう言うことは、10代の女の子なら誰でも興味が出る年頃だと思う。
むしろ早熟なのは言葉選びや表現の方だ。言い回しの妙は、才あってのものだと思う。あの多感な時期に想いや感情は目まぐるしく動くが、それを順序立てて文章にするのなかなか出来ることではない。
だが、(不自由な生活を送ってはいるけれど)普通の思春期の女の子の日記だった。
プライベートな日記を盗み読む背徳感すらある。むしろ男性は読みにくいのではないか…これは同世代の少女たちが読むべきだと思う。
私は彼女の晩年を知り、そして、その生きていた場所を実際に見てきた。
アンネの日記を読みながら、頭の中で何度も再生される収容所での様子が頭をチラついてしまう。12〜14歳の彼女が喧嘩し、怯え、恋し、ユーモアを交えて笑い、夢を語り、クルクル動く感情のその全ての文章の隙間に、対極にある収容所での姿が常に重なり、本の中の彼女が生気に満ちていればいるほど、その落差に胸が苦しくなった。原文ではないから、果たしてどれほど翻訳の妙が冴え渡っているかわからないけれど、10代の感性が飛び跳ねていた。
アンネフランクをよく早熟な少女と表現することがある、例えば、異性や性に対してもあけすけなく興味を持っていたし、人間観察も自己分析もよくしていた。
近年、アンネの日記の、いわゆる”袋とじ”部分の解析ができて、性的なジョークが書かれていたと発表された。でも、そう言うことは、10代の女の子なら誰でも興味が出る年頃だと思う。
むしろ早熟なのは言葉選びや表現の方だ。言い回しの妙は、才あってのものだと思う。あの多感な時期に想いや感情は目まぐるしく動くが、それを順序立てて文章にするのなかなか出来ることではない。
『アンネフランクの記憶』 小川洋子著

“……we were no heroes, we only did our human duty, helping people who need help.“
(by ミープ・ヒース。フランク一家の最大の協力者であり家族のような友人であったミープさんの言葉を本文から)
小川洋子さんの”ものを書くこと”の原点となっている、少女時代に読んだ『アンネの日記』。そのアンネの足跡を辿り、ドイツ、オランダ、ポーランドへ、ご存命のアンネの知人たちに会い、そして、小川さんがアンネに会いに行く本。
『コルベ神父―優しさと強さと』 早乙女 勝元著
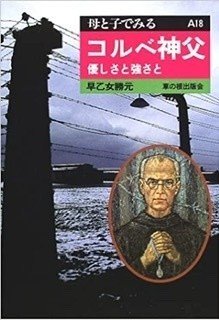
キリスト教関連の出版社以外での、コルベ神父についての本を読みたかったので。
『アウシュヴィッツ博物館案内』中谷剛著
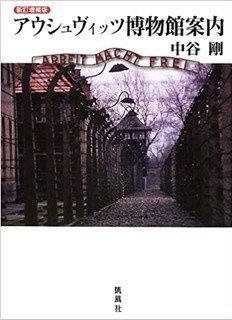
アウシュヴィッツのガイドをしてくださった、アウシュヴィッツ博物館の日本人唯一の公式ガイドをされている中谷剛さんの本。
『服従の心理』 スタンレー・ミルグラム著

権威による命令で、人は殺人ができるのか?という、心理学実験でとても有名な、通称“アイヒマン実験”について。
0 件のコメント:
コメントを投稿